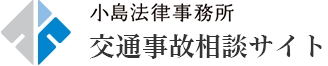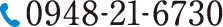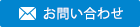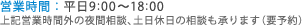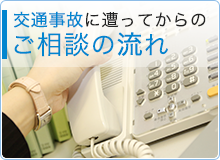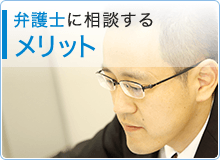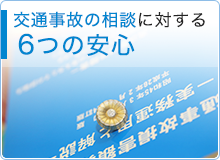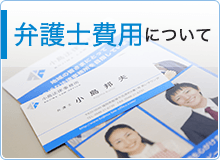違反しがちな道路交通法違反(ハイビーム)
2024.07.26更新
道路交通法上、夜間における自動車の走行については、ハイビームで走行することが基本となっています(道路交通法52条1項、2項)。
では、以下の事例におけるハイビームの使い方は、道路交通法に違反するでしょうか。
夜間、片側1車線の道路を、ハイビームで直進中に、対向車線を自転車が自車に向かって直進していました。ロービームでは、自転車の姿が見えにくくなるため、車の運転者は、ハイビームのまま直進して、自転車とすれ違いました。
この点、自転車とすれ違う際に、ハイビームからロービームにしなかった運転者は、道路交通法52条2項違反にあたる可能性があります。
第52条
「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。」
ハイビームのまま自転車とすれ違ったことから、上記の「他の車両等の交通を妨げるおそれ」にあたるのかが問題となります。
この点、「他の車両等の交通を妨げるおそれ」とは、前照灯の照度が強いため、これと行き違い又は先行する車両等の運転者がげん惑され、運転に支障をきたすおそれがあるときと解されています。
そのため、上記事例では、ハイビームの強い光によって、対向車線を直進する自転車の運転者がげん惑されるおそれがあるため、道路交通法52条2項違反となる可能性があります。
そして、道路交通法52条2項に違反した場合、5万円以下の罰金の処分を受ける可能性があります(第120条1項6号)。
投稿者: