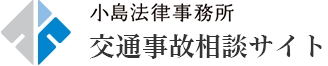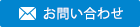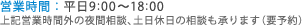盗難車の所有者の責任3(自賠法)
2020.03.26更新
飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「盗難車の所有者の責任 3(自賠法)」についての解説です。
前回の稿(盗難車の所有者の責任2)では盗難車の所有者の不法行為責任を説明しましたが、今回は自動車損害賠償責任法(以下、「自賠法」といいます)3条の運行供用者責任を説明します。
自賠法は、自動車による交通事故によって、生命・身体が害された場合に、その被害者を確実に救済することを目的とする法律です(自賠法1条)。その意味で、自賠法には民法の不法行為責任の特則的な性格があります。
まず、自賠法3条本文は「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定しています。「運行」という言葉は、自賠法2条2項において「・・・自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう」と定義されています。
この条文を分析すると、自賠法3条は、民法709条(不法行為)と2つの大きな違いがあることがわかります。
まず①自賠法3条は、民法709条とは違い、「故意・過失」が成立要件になっていません。ですので、この点は被害者側に有利な取り扱いになっています。他方で②自賠法3条では「他人の生命又は身体」に賠償の対象が限定されています。そのため、民法709条とは違い、人身損害のみに適用される点で、その賠償責任の範囲が限定されています(ですので、全稿までに紹介した令和2年1月21日の最高裁判決の事案のように物損事故しか生じていない場合には、自賠法は使えないということです。)。
つまり一般的には、人身損害であるならば、民法709条に基づく損害賠償請求よりも、自賠法3条に基づく損害賠償請求の方が認められやすいといえます。同条に基づく責任を運行供用者責任といいます。
では、人身損害であれば、泥棒運転による事故であっても、その被害者は自賠法3条本文によって車の所有者に対して運行供用者責任を追及することが可能であるといえるのでしょうか。
この点、最高裁は自賠法3条本文の「自己のために自動車を運転の用に供する者」とは「自動車の使用について支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者」であると解しています(最判昭和43年9月24日 判時539号40頁)(ちなみに、この判例は盗難事件について判断されたものではありませんが、その後盗難事件における所有者の損害賠償責任が争われた最高裁昭和48年12月20日判決(民集27巻11号1611頁)等において踏襲されています。)。
要するに最高裁は、泥棒運転において所有者が自賠法3条の運行供用者に該当する場合とは、所有者が①盗難車を支配し②その使用による利益も自身に帰属するような場合であると理解していると考えられます。
この最高裁の判決後に、裁判例上これが認められたケースもありますが、否定されたケースもあります。その判断材料は多岐にわたりますが、例えば、鍵の保管状況であったり、駐車の場所であったり、盗難届の有無、盗難場所から事故発生までの時間的・場所的な間隔が参照されているようです。
このように、判例や裁判例を前提にすれば、泥棒運転による事故に限っては、人身被害者の自賠法3条に基づく所有者に対する損害賠償請求は不法行為に基づく損害賠償請求と同様、高いハードルがあるといえるでしょう。
投稿者: