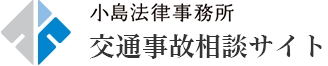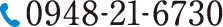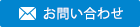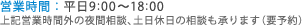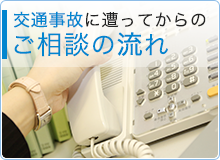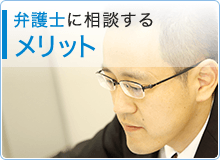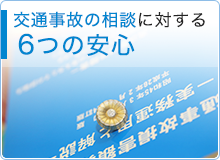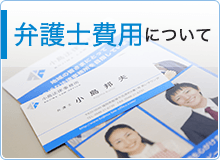違反しがちな道路交通法違反(青信号に変わっても前方車両が動かない時のクラクションについて)
2024.05.09更新
飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「青信号に変わっても前方車両が動かない時のクラクション」についての解説です。
信号機が赤から青に変わったにもかかわらず、前方車両が停止したままであった時、前方車両の運転手に、青信号へ変わったことを気付かせるため、クラクションを鳴らした経験がある方も多いかと思います。
この点、上記のように、信号が変わったことを気付かせるために、クラクションを鳴らした場合、以下のとおり、道路交通法54条2項違反に該当する可能性があります。
道路交通法第54条
(警音器の使用等)
「車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」
この点、「危険を防止するためやむを得ないとき」とは、「警音器(クラクション)を鳴らすほかに危険を防止することができない場合」と解されています。
そのため、信号が変わったことを気付かせるためにクラクションを鳴らすことは、「危険を防止するためやむを得ないとき」に該当しないため、道路交通法54条2項違反になる可能性があります。
そして、道路交通法54条2項に違反した場合、2万円以下の罰金又は科料に科される可能性があります(第121条1項9号)。
道路交通法第121条
「次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 …
…
九 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者」
投稿者: