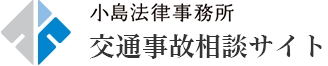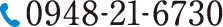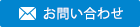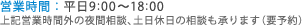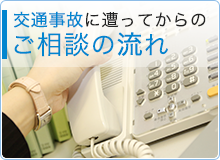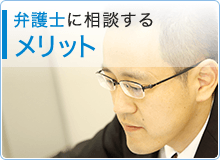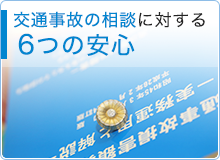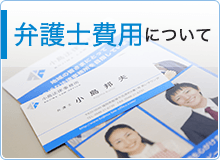LAC基準 令和3年版
2021.11.17更新
飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「LAC基準 令和3年版」についての解説です。
【LAC基準】
交通事故が発生した場合には、被害者は自身の契約している損害保険会社(以下「損保」といいます)の保険商品である弁護士保険(弁護士費用特約)を利用することにより、弁護士費用を保険で賄うことができます。その場合には、弁護士を無料で利用することができます。
その弁護士費用について、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が損保と協議のうえで予め定めている保険金支払基準のことをLAC基準といいます。
この基準を定めることにより、損保から弁護士に支払われる費用の統一化・明確化が図られますから、交通事故の被害者と弁護士との契約もスムーズに行えるようになります。なお、支払基準の詳細は、LACが発行している通称「LACマニュアル」に記載されています。
多くの損保・共済は、弁護士保険の支払基準について、LACと協定を結んでいます。協定を結ぶことで、その損保・共済及び契約弁護士は、それぞれLAC基準を尊重する必要が生じます。2021年7月1日現在、協定を結んでいる大手の損保・共済は以下のとおりです。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
AIG損害保険株式会社
au損害保険株式会社
キャピタル損害保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
ジェイコム少額短期保険株式会社
セゾン自動車火災保険株式会社
全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
全国自動車共済協同組合連合会
全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop〈全労済〉)
ソニー損害保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
大同火災海上保険株式会社
Chubb損害保険株式会社(チャブ保険)
中小企業福祉共済協同組合連合会
チューリッヒ保険会社
ミカタ少額短期保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井ダイレクト損害保険株式会社
楽天損害保険株式会社
一方で、協定を結んでいない損保・共済は、以下のとおりです。
アクサ損害保険株式会社
アメリカンホーム医療・損害保険保険株式会社
イーデザイン損害保険株式会社
SBI損害保険株式会社
ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド
セコム損害保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
日新火災海上保険株式会社
日本再共済生活協同組合連合会
明治安田損害保険株式会社
【損害サービスセンター】
損害サービスセンターとは、保険契約の対象者からの事故の連絡を受けて、事故状況や被害の状況を確認し、事故対応を行う部署のことをいいます。
そして、事故受付後は、専任担当者が窓口となり、事故の対応を行います。
筑豊地区にある損害サービスセンターとしては、以下の損保・共済があります。
損害保険ジャパン株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
全国共済農業協同組合連合会
投稿者: