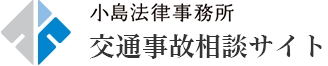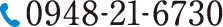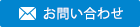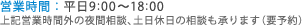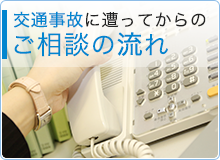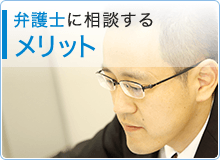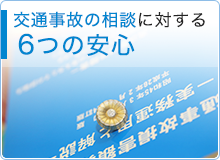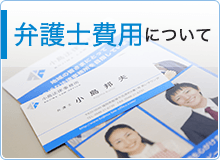オートライトの義務化
2021.03.12更新
飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「オートライトの義務化」についての解説です。
【オートライトの義務化】
道路運送車両の保安基準が改正され、新型車は2020年4月から、継続生産車は2021年10月から普通乗用車のオートライトの装備が義務化されます。
オートライトとは、周囲の明るさに応じて、ライトの点灯/消灯を自動的に行ってくれる機能のことです。
【改正点】
今回の改正で定められたオートライトに関する主な新保安基準としては、以下の3つが挙げられます。
①周囲の照度が1,000ルクス未満になると、2秒以内に点灯する
なお、1,000ルクスの照度とは、JAFの説明によると、信号や他車のブレーキランプなどの点灯が周囲から目立ち始める時の明るさとされています。イメージとしては、夕暮れの暗くなり始めるころの時間帯になります。
②周囲の照度7,000ルクス以上になると、5秒から300秒以内に消灯する
点灯から消灯までの応答時間は自動車メーカーに委ねられています。
③走行中、手動でオートライト機能を解除することができない(ただし、駐停車状態にある場合は消灯可能)
【オートライトの義務化の背景】
1 従来のオートライト機能には、メーカーや車種によってライトの点灯タイミングに差があり、明確な基準がありませんでした。そのため、同じ時間帯なのに、ライトが点いている車と無灯火の車が混在している状態でした。
2 また、ヘッドライトを付ける時間帯については、道路交通法は、「夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)」と定めています(道路交通法52条1項)。この「日没から日の出までの時間」については、日付や場所によって様々で、その時間を把握することが困難なこともあり、ドライバー個人の感覚でヘッドライトを点けていた状態が多かったと思われます。そのため、法的には夜間にあたる時間帯でも、無灯火で走行している車両も少なくありませんでした。
3 さらに、都市部や市街地では、道路の照明や店舗の照明が多くあるため、ドライバーが回りの明るさに気付かずに無灯火で走行してしまう場合もあります。
これらを背景としたヘッドライトの無灯火を原因とする事故を防止するために、今回のオートライトの義務化が行われることになりました。
投稿者: