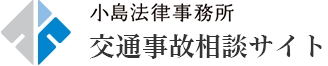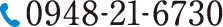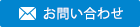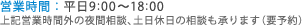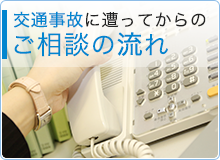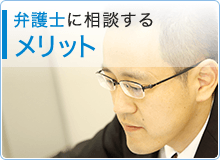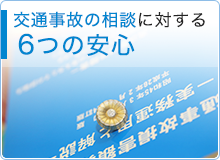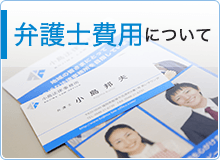特殊な改造の施された車両の時価額
2019.10.04更新
飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「特殊な改造の施された車両の時価額」についての解説です。
以前の「車両時価額の算定方法」の項目でも解説したとおり、車両の時価額を算定するかは容易ではありません。この点、特殊な改造が施された車両の時価額についても、大きな争いになることがあります。
これについて参考になる裁判例のひとつに、大阪地裁平成8年3月22日判決(事件番号:平成7年(ワ)6861号)があります。
この事件は被害者が300万円で購入し、さらに280万円と140万円をかけて、塗装、マフラー、エンジン等に改装が施された高級外車が、購入から約5年後、道路脇に駐車されていたところに加害車両が追突したというものです。被害者は加害者に対して、その車両の損害額として、改装を含めた時価相当額である400万円を請求しました。
それに対して裁判所は、「各改装は専らカーマニアとしての趣味を満たす目的でなされたものと認められる」から、被害車両に「客観的価値の増加があったとは認められない」と判示し、同じ高級車両の他の市場価格なども参考にしつつ、原告の車両購入費用300万円の6割である180万円のみを車両の損害として認め、改造費用を認めませんでした。
裁判所としては、車両に相当の金額を用いて改造・改装が加えられているとしても、それが個人の趣味趣向に基づくものに留まるものである場合には、車両の時価額を向上させる事情としてあまり考慮しないという姿勢をとったものだといえるでしょう。
また、この裁判例からすると、例えば車高を低くしたりとか、マフラーを改造したりすること等も個人の趣味に基づくものといえますから、事故の際には、その改造費用について裁判所は損害として認めない可能性があるといえます。
ただし、この裁判例自体が20年以上前の事案ですし、改造車であってもその改造費用まで損害と認められることもありますから、現実にはケースバイケースです。
投稿者: