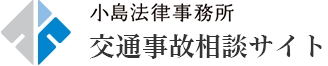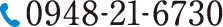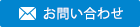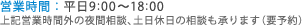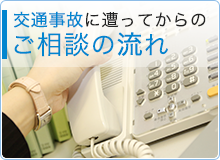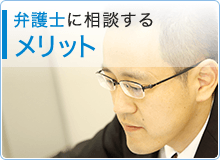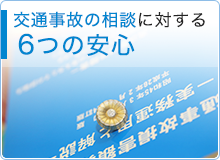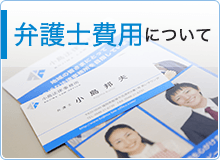道路交通法改正(自転車)
2020.02.21更新
小島法律事務所より、弁護士による「道路交通法改正(自転車)」について、道路交通法改正点の解説です(前回の記事はこちら)
自転車の事故を防止するために平成27年から始まり話題になった制度を紹介します。
平成27年6月、道路交通法の改正法が施行されました。その中で、自転車に関して新たに「自転車運転者講習」の受講命令制度が設けられました(道路交通法108条の3の4)。
これは、自転車を運転する者が、信号無視や通行区分違反など14種類が定められている「危険行為」(道路交通法施行令41条の3)で警察に摘発され、3年以内に再び摘発された場合に、その違反者に対し、各都道府県の公安委員会が、自転車の安全に関する講習を受講するよう命令できる制度です。ちなみに、対象は14歳以上です。
これまで自転車は、自動車のように反則金の制度がなく、違反すなわち刑事罰という構造になっていたため、よほどのことがない限り違反が見逃されてきたという経緯があります。ですので、この自転車運転車講習制度によって、自転車の違反に対する制裁が容易になりました。
都道府県公安委員会からこの講習の受講命令が発せられた人は、一定額の受講料を修めて、3時間程度の安全講習を受けなければなりません。受講場所は各都道府県公安委員会の指定の場所です(通常は、自動車免許センターで行われるようです)。
この安全講習の受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金という刑罰に科されることがあります(120条1項17号)。
内閣府の発表によると、危険行為として摘発されたものは、ブレーキが無い自転車を運転する等の整備不良か、信号無視が大半を占めています。
さらに、内閣府の発表によれば、施行後1年で講習がされたのは24件です。また、危険行為として摘発されたのは48件です。3年以内に2回の危険行為で講習が義務付けられるという仕組みですから、講習が命じられた24人以外は、誰も危険行為での摘発がされていないように読み取れます。
ちなみに、直近でのデータが見当たらないため、自転車運転者講習の現在の運用は不明です。
投稿者: